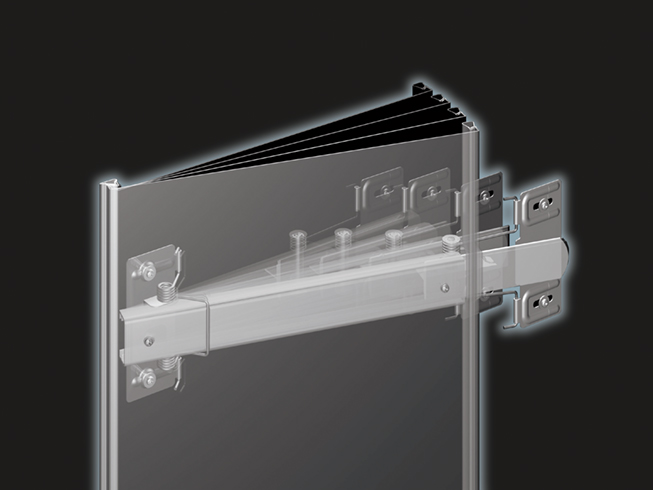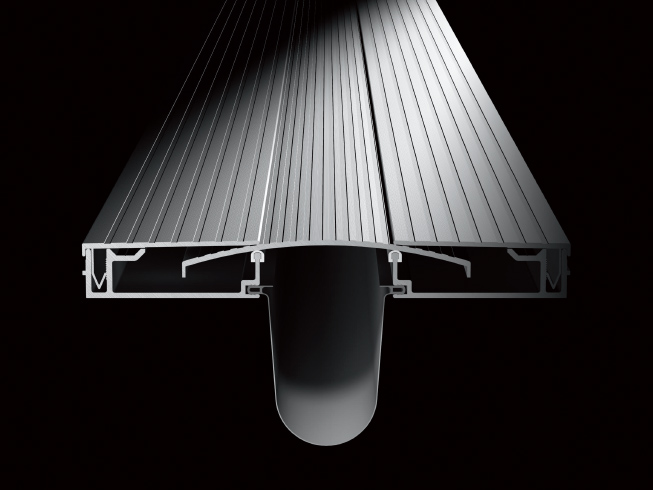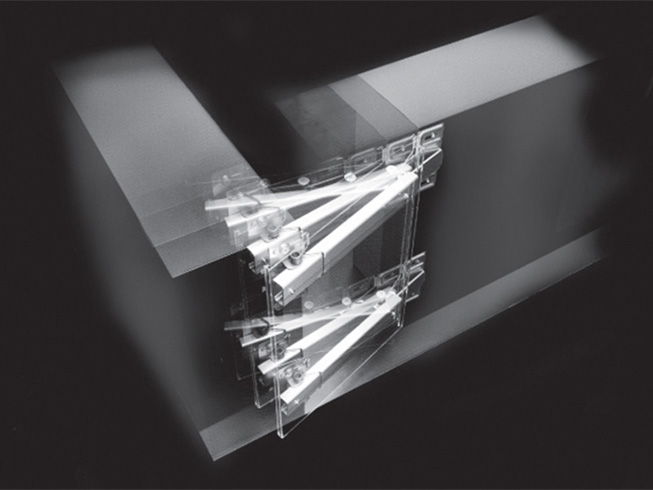基本原則は「安心」の色彩環境づくり
建築空間の色は、人の心に働き掛ける
建築空間をつくるとき、床・壁・天井の色をどのように選んでいますか。人間を包む色は、そこにいる人の心に働き掛け、心理状態に大きな影響を与えます。色選びは、おろそかにできません。
このコラムでは、医療福祉施設を例に、色選びのポイントを解説していきます。
空間づくりは、そこで過ごす全ての人にとっての居心地の良さを追求するものです。商業施設も医療福祉施設も、もちろん共通です。
ただ、医療福祉施設ならではの特性があります。例えば、加齢や病気によって心身ともに衰えた高齢の患者や入所者は、居場所を自由には選べません。とりわけ医療施設では、病棟からも病室からも外に出られない患者が少なくないでしょう。病院内の環境が全てだからこそ、居心地の良さは不可欠な要素です。
それを、どう実現するか――。
重要な視点は、患者や家族の不安軽減
医療施設のインテリアへの要望は多種多様です。「明るさ」「素材感」「景観との調和」「存在感」「温かさ」......。さまざまな要望に応える必要があります。
これらの中で最も重要なのは、「患者・家族の不安軽減」という視点でしょう。医療施設で時を過ごす患者・家族は、これからどうなるのかという不安にさいなまれます。その不安の軽減を図ることが、居心地の良さを実現するためにまず求められることです。
もう一つ重要な視点は、スタッフの就労環境改善です。患者・家族だけではなく、スタッフも1日の多くを施設で過ごします。スタッフにとっての居心地の良さも、療養空間を整えるために必要なのです。
これら2つの視点を踏まえ建築空間づくりを進めていくうえで、色選びにはどう臨めばいいのでしょうか。キーワードは「安心」です。患者・家族にとっても、またスタッフにとっても、安心できる色彩環境づくりこそ、医療施設で重点を置くべき方向性です。
4段階のプロセスで色を選ぶ
現地を歩き、五感をフル活用
色選びには、エビデンスが必要です。
色を選ぶのは、誰にでもできそうです。しかし、十人十色と言うように人の好みは異なります。個人の好みがそこで求められているイメージと一致するとは限りません。「この色の組み合わせが、きれいだから」という理由だけでは、説得力に欠け、誰も納得させることはできません。
●エビデンスの一つに色の生理的効果

資料提供:カラリスト・梅澤ひとみ氏
では、エビデンスをどのように得ていくか。そこは、専門家それぞれで流儀は異なると思います。ここでは環境カラリスト・梅澤ひとみ氏の色選びのプロセスをご紹介します。大きく分けると、①現地調査②ゾーニング③サンプル収集④色とトーンの決定――という4つのステップを踏みます。
最も重視するのは、「現地調査」です。敷地周辺を、風を感じながら歩くステップです。その地域がどのような歴史をたどり、どのような自然環境を持つのか、またそこでどのような生活が営まれているのか。そうした情報は、インターネットで収集するより、五感をフル活用して感じたほうが、量も質も豊富に得られます。時として、歩くと「天から色が降って来る」こともあります。地域を歩き回る中で、インテリアのモチーフや色選びのヒントを得ていくのです。
コンセプトを固め、色のイメージを描いていく
●「PCCS(日本色研配色体系)」トーンのイメージ

出典:日本色研事業株式会社
このステップではもちろん、運営理念を調べたり、図面から動線などを読み取ったり、地域関連の資料を集めたりするなど、机上の作業にも取り組みます。そのうえでキーワードを抽出し、インテリアに関するコンセプトを固め、色のイメージを描いていくのです。この段階では、色見本は、DICグラフィックスのカラーガイドや米ベンジャミンムーアのサンプルシートを用います。
さらに「ゾーニング」では機能ごとに施設内をいくつかのゾーンに分け、「サンプル収集」では具体的な検討に向け仕上げ材のサンプルを集めます。「色とトーンの決定」では、ゾーンにふさわしい色とトーンを、色見本と収集した仕上げサンプルを基に決めていきます。
<事例紹介>中部国際医療センターでの色選び
現地調査で感じた力強さを色で表現
色選びの具体例として2022年に開院した中部国際医療センター(502床、設計:久米設計)の例をご紹介します。地域の中核病院としての機能を担いながらも、メディカルツーリズムを視野に入れ、2024年には陽子線がん治療センターも開設しています。
冒頭の写真は、1階正面玄関から続くホスピタルモールです。世界を見すえたパワフルな計画なので、インターナショナルな空港や駅のコンコースのようにアクティブ感のある空間をイメージし、明度や彩度にメリハリを付けた配色を取り入れています。
先ほどご紹介した色選びのプロセスに沿って各ステップを振り返ってみましょう。
まず「現地調査」です。周辺地域を歩きながら感じたのは、「底力」です。一見静かなまちでありながら、Uターンで戻った若者の土地への愛着にそうした力強さを感じ、1階ホスピタルモールの色選びでは明度や彩度のメリハリを通じてその力強さを表現しています。
次に「ゾーニング」です。エントランス、外来、待合室、手術室、......。病院は多機能で、それぞれに求められる機能があります。その機能にふさわしい仕上げ材や色のトーンを選びます。例えば、重量のある機器の移動が多いゾーンであれば、耐動荷重性の高い床材を選ぶ、という具合です。ゾーンで求められる機能にふさわしいというのは、説得力のある理由になります。
心理的効果や生理的効果にエビデンス
「サンプル収集」は、まず床材から始めます。壁材に比べ選択肢が少ないため、そこからまず決めておく必要があるからです。床材一般に求められる機能は、耐久性の高さです。医療施設である以上、長寿命が求められます。床材をはじめ材料費が高騰する中、コストの制約はありますが、ゾーンごとにメリハリを付けるなど工夫しながら、耐久性の高さを追求していきます。
最後の「色とトーンの決定」では、色の心理的効果や生理的効果という視点に立つと、エビデンスを学術面から主張しやすくなります。心理的効果は、色から受けるイメージです。例えば「赤」なら、「暖かい」「積極的」「活動的」などのイメージが上がります。また生理的効果は、色が身体に与える生理作用です。同じ「赤」には、「筋肉の緊張」「血圧上昇」などの作用が見られます。これらの効果を踏まえ、統一感とバランスに配慮しつつ、色とトーンを決めていくのです。
こうして決めた色とトーンを、ゾーンごとにいくつかご紹介します。
●中部国際医療センターはモノトーンを基調

左上は外来、右上は病棟。左下は救急エリア、右下は職員食堂
写真提供:環境カラリスト・梅澤ひとみ氏
外来や病棟は、動線やトイレも含め、ベースはモノトーンで統一しています。病棟スタッフステーションの壁面は色に変化を付け、スタッフの位置認識を助けています。
職員食堂は、床材に個性的な木目調塩ビシートを用いています。外来や病棟のモノトーンとの中で色相に変化を付け、スタッフがリフレッシュできるように配慮しています。
救急エリアでは、ベースカラーを引き立てるアソートカラーやアクセントカラーに青を用いています。青には、筋肉の緊張を和らげ、呼吸や心拍を安定させる、生理的効果が見込まれます。鎮静効果が期待できる配色がスタッフと患者の興奮を鎮めたいこのゾーンにはふさわしいという考え方に基づいた色使いです。
本コラム内に掲載している施工例写真については、環境カラリスト・梅澤ひとみ様からご提供いただきました。
エービーシー商会では、さまざまな種類の床材を取り揃えております。今回のセミナーテーマである「医療福祉施設」にも最適な建材がございますので、ご参考にしていただけると幸いです。
- 1
- 2